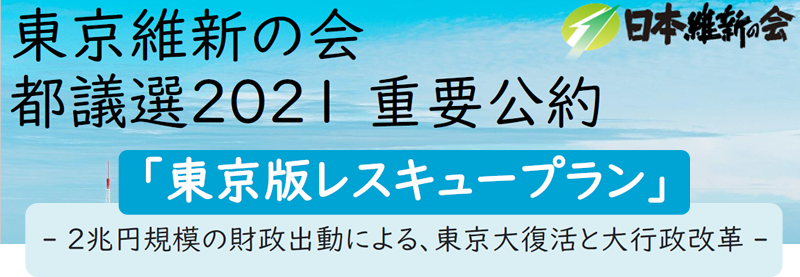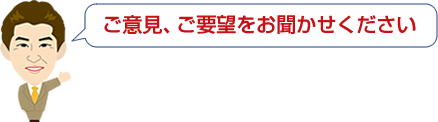都議会レポート2011/3

平成23年第1回都議会定例会が、3月11日に終了しました。
閉会直後には、大規模な東北地方太平洋沖地震が発生しました。被災された方々には、心よりお見舞いを申し上げます。
都議会最終日、石原知事は4期目の出馬を表明しましたが、石原知事が引き続き都政に携わることになれば、都政刷新の機会が失われることが懸念されます。
私たち都議会民主党は、新たな都政のもと、都政改革に取り組んでいく所存です。都民の皆様の変わらぬご支援・ご協力をお願い申し上げます。
関係者の合意なき築地市場豊洲移転に反対!

都議会民主党は、築地市場移転について、移転予定地の安全性が確認されていないことや関係者の合意も得られていないことから、強引な移転に反対してきました。
昨年10月の石原知事の豊洲移転宣言後も、地元・中央区からの要望が提出されたことや水産仲卸業者の総代選で移転反対派が過半を占めたことなどの経過を踏まえれば、関係者の合意が得られているとは言い難い状況にあります。
また、都は、土壌汚染対策工事を実施しても、法律に基づく区域指定が解除されないことを認めています。
築地地区のまちづくりについて、都は「築地の場外と場内とが一体となって育んできた食文化の拠点としての活気と賑わいの継続という観点から地元区などと協議する」と踏み込みましたが、納得できる内容ではありませんでした。
これらのことから、都議会民主党は、市場会計から豊洲市場関連経費の一部を削除する修正案を提案しましたが、予算特別委員会では18対20で修正案が否決され、都議会本会議で、63対62で知事原案が可決されました。
新年度予算で、都民の命と生活を守る更なる取組みを

都は、景気が持ち直しつつあるものの、引き続き厳しい雇用情勢などに対応するため、若年層への就職サポートや円高で経営が苦境にある中小企業への支援など、都民が抱える不安への取り組みを強める予算を編成しました。
都議会民主党は、なかなか短縮されずに延びている救急搬送時間への対応や、木造住宅密集地域の耐震化推進、緊急輸送道路沿道以外の分譲マンション建替支援など都民福祉の向上のため、更に取り組むべき課題があると指摘するとともに、都民に事業成果を積極的に示していくべきと求めました。
東京の成長戦略で経済に活! 中小企業の販路拡大が前進
都議会民主党が、東京の将来像として、アジアのヘッドクォーターとなるべく、特区の創設も含めた都の取り組みを求めたのに対し、石原知事は「新たな制度の活用も含め、検討していく」と答弁しました。
また、都議会民主党は、GDPで中国に抜かれる中、東京の労働生産性を向上するためのイノベーション支援も提案しています。
さらに、中小企業対策では、国が、緊急保証制度を22年度末で終了する中、都の支援充実を求めたのに対し、都は「小規模起業者に対する保証料の2分の1補助の継続や500億円規模の円高対応融資メニューを創設する」と答弁。加えて、中小企業の海外販路開拓支援でも、ナビゲーターを倍増することや海外展示会への出展機会の拡充などを約束しています。
就職氷河期に新事業創設 未内定者の正規雇用の促進を

就職氷河期と言われる中、東京都は、新たに未就職卒業者緊急サポート事業を立ち上げます。これは、優れた人材を求める中小企業と、中小企業に目がいかない学生とのミスマッチを解消するもので、企業と学生とのマッチングや職業体験を通じた上で、正規雇用化を促進するものです。
また、高校生の就職活動では、進路指導教員への支援が重要であり、都議会民主党の質問に、都も「進路指導者向けセミナーの開催など、学校現場と密接に連携して取り組む」と約束しています。
「暴力団排除条例」が可決・成立 誰もが暴力団との関係遮断へ

これまでの暴力団排除活動は、いわゆる「3ない運動」で推進されてきましたが、今回の条例は、更に「交際しない」という新たな理念を加えて、暴力団を社会的に排除していこうというものです。
私たちは、意図せず関係を持ってしまった事業者などには、丁寧に関係遮断を促すこと、暴力団の妨害行為には、警察が万全の保護策をとることなどを求めました。
警視総監は、「暴力団に指一本触れさせないという強い覚悟をもって、都民の安全確保に万全を期して」いくとしています。
支え合いと活気ある 「新しい公共」の社会へ
「新しい公共」の社会とは、公共を担うのは、「官(かん)」であるという考え方から脱却し、日本に古くからある支え合いの仕組みに加え、新たな社会を支え合う仕組みを作りあげることです。
東京都には6億円の「新しい公共」に向けた支援基金が設置されました。都には、この基金を有効に活用し、新しい公共の担い手となるNPO法人等への財政安定化など、自立に向けた積極的な支援強化を求めました。
また、国では寄付文化の醸成に向けて、寄付をした際の税額控除拡大など、様々な制度を検討中です。都は、それに対し、いくつか欠陥を提示しましたが、理念には賛同しています。そのため、着実な課題解決と、「新しい公共」の実現に向け、都の積極的な取り組みを今後も求めていきます。
認知症疾患医療センター 都内12ヵ所整備へ
全国で90ヵ所以上ある認知症疾患医療センターが、ようやく都内にも整備されます。
これにより、認知症の鑑別診断まで数ヶ月待ちという状況の改善や、地域の医療機関や介護関係者が連携した対応などが期待されます。また、一般の施設や病院では対応が困難な(※)BPSDや身体合併症受け入れのための基幹型センターの整備も今後必要であるため、あわせて代表質問で質しました。
都は、センターが患者に応じた適切な医療機関を紹介し、迅速な診断、医療・介護連携協議会や事例検討会を通じた関係機関とのネットワーク構築などを行うとし、都が標準的な地域連携パスの作成を支援すると答弁しました。指定拡大は、今後の運営状況を踏まえ検討すると答えました。
※行動心理症状(攻撃的行為、不潔行為、異食など)
救急搬送時間短縮へ 取り組み強化をせよ

救急搬送時間は、傷病者の救命率に影響するものであり、あらゆる体制・取り組みを強化し、その短縮を図らなければなりません。
都議会民主党は、繰り返し救急の受け入れ不能の原因とされる医師や空き病床の不足、医療機関同士の連携や救急電話相談体制の拡充など、さまざまな緊急対策を求め、多くが実現しました。
しかし、救急搬送時間は年々延びています。1件1件の搬送案件を詳細に分析し、更なる対応策を検討すること、明らかに不要なケースは現場トリアージを求めるなど、改善の積み重ねを求めました。
虐待対策強化が実現!

児童相談所の虐待相談受理件数は、平成21年度3366件と10年前の2.6倍へと増加しており、大変過密な状況です。また、区市町村からは、都による専門的支援の強化が求められており、都議会民主党は、対応強化を求めてきました。さらに、すべての先駆型子供家庭支援センターへの虐待コーディネーター配置や虐待対策ワーカー増配置に向けて、都の取り組み強化を求めました。
都は、すべての児童相談所に児童福祉司を増員し区市町村との調整機能をより強化する、区市町村への財政支援では3ヵ年補助率をかさ上げすると答弁しました。
障害グループホームに重点的取り組みを
都の障害者の就労支援・安心生活基盤整備3ヵ年プランは、平成23年度で最終年です。計画では1640人分のグループホーム定員を増加し、5514人分とすることとなっています。そこで、計画達成に向けた取り組みと、国の新たな家賃助成1万円を利用者負担軽減に活用すべきとして、都の見解を質しました。
都は、目標達成に向けて事業者への働きかけを強化し、整備が十分でない区市町村への重点的な働きかけを行うと答えましたが、家賃助成については、国から詳細が示されていないとし明らかにしませんでした。
都議会民主党は、引き続きグループホーム等の設置促進の次の展開に向け都営住宅建て替えにより創出される土地の活用など、一層の施策を求めていきます。
がん手帳本格実施へ 活用マニュアル整備
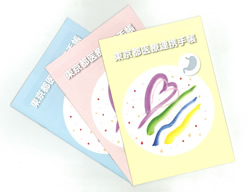
都議会民主党が策定・発行を求めてきたがんの東京都医療連携手帳、いわゆる東京都がん手帳が試行を経て本格実施されます。
これは拠点病院等と地域の医療機関の双方が治療経過等きめ細かい情報を共有するための医療連携ツールです。また、患者自身が治療を理解し、記録することを通じてがんとの向き合い方を考えることにも役立ちます。
今後の本格実施に向け、拠点病院等での説明会に加え、患者、医療機関に対する活用マニュアルを策定することとなりました。
検診受診率50%達成へ 個別の受診勧奨強化を
東京都におけるがん検診受診率は、約30%と全国的にも最低レベルです。検診受診率が高くなればその分、がん死亡率が減少することが実証されています。
そのため、都議会民主党は、がん検診受診率向上が急務であると考え、研究で受診率向上に有効な取り組みとされている、対象者個々への受診勧奨、再勧奨の取り組みがすべての区市町村で実施されるよう都が支援すること、企業における取り組みが進むよう積極的に働きかけるよう求めました。
都は、包括補助を行うとともに効果が認められた取り組みを周知することにより、実施地区の拡大を図っている、職域での取り組み促進のため、がん検診推進サポーター認定や企業や健康保険組合に対し情報提供していると述べるに止まりました。
学校・家庭・地域の連携強化を!
複雑化した社会に比例して、教育へのニーズも高まり、学校は多くの課題を抱えています。
本来、教育は学校だけでなく、家庭や地域など、様々な関係者が相互に取り組むことで、成り立つものです。
これまでの全国の(※)学校支援地域本部事業の取り組みは拡大傾向にある一方、都内の各学校では、地域コーディネーターやボランティアなどの地域人材の養成、確保が困難といった課題があります。都においては、区市町村の学校支援ボランティア推進協議会の設置を一層支援するよう求めました。
※学校支援地域本部事業・・・地域の学校支援ボランティアなどの学校参画をコーディネートする国の事業。平成20年度より始まり、23年度からは新たな事業にて地域連携を支援する。
校務改善で活気ある学校運営づくりを
都教育委員会は、小中学校の教職員における業務実態調査結果と今後の方向性を「小中学校における校務改善の方向性について」の報告書として、取りまとめました。
その中で、業務負担・多忙感発生の要因として、環境変化に追いつかない旧態依然たる運営体制、組織風土が挙げられています。
その解決策の一つとして、副校長の直轄に経営支援部(仮称)を設置することが検討されていますが、教職員全体の学校経営に対する参画意識が高まり、組織の一体化が強まる施策とするよう、都議会民主党は求めました。
また、教職員に対する表彰制度の拡充など、意欲向上に向けた取り組みや、ICT等のスキルアップ支援で校務の効率化が図れることを改めて求めました。
被害者支援は目標を掲げ実効性あるものとせよ!
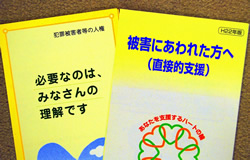
都の新たな「犯罪被害者等支援推進計画」は、総合相談窓口の周知に関する具体的な取り組みや職員研修の規模が記述されていない等、不明な部分が散見されます。
都議会民主党は、平成23年度計画の取り組みとして、具体的に犯罪被害者支援がどこまで推進されるのかを問いました。それに対し都は、改定した計画を着実に推進し、支援の充実・強化に努めると答弁しました。
都議会民主党は、都が数値目標を掲げた被害者支援計画を策定することが重要と訴えています。
立ち直りを目指す青少年を東京の社会全体で支えよ!
東京の将来を担う青少年の中で、犯罪を犯した青少年が、立派に更正を果たしているケースが多い一方で、犯罪を再び犯すケースがあることから、都は、立ち直り支援策を行っています。また、国は、出院者の立ち直りを地域で支えている保護司の皆さんを組織的に支援するため、全国に更正保護活動サポートセンターを設置することとしました
都議会民主党は、センターが都内に設置されていく中、保護司会から施設貸与の協力要請があれば対応していくべきと求めました。
都は具体的な要望があれば、財産利活用の原則を踏まえ、考慮・検討する旨の答弁を行いました。
都議会民主党は、都の協力が青少年の立ち直りや地域の安全・安心に寄与すると主張しています。
緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断を義務化
建築物の耐震診断・改修の実施は、現行の耐震改修促進法では努力義務にとどまり、所有者の意思に委ねられていることから、対策の進展には限界があり、耐震化は進んでいません。
今定例会では、特定緊急輸送道路の指定、その沿道建築物の所有者に対する耐震診断の実施義務、耐震改修等の実施の努力義務、耐震化に要する費用の助成などを内容とする「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」が可決されました。
都議会民主党は、建築物の耐震化については、その対象を限定せずに進めるべきと考えてはいますが、この条例を、建築物の耐震化促進に向けた施策として、これまでより一歩踏み込んだ内容となっているものと、一定の評価をしています。
日本橋再生に向け都心環状線撤去検討を
今年4月3日、日本橋が石造り2連アーチになって架橋100周年を迎えます。
日本橋再生は、有識者会議で日本橋地域における首都高の撤去、移設、地下化等について議論が行われ、平成18年9月、総理大臣宛に、民間主導による街づくりを先導する、街づくりによる首都高移設費用を低減する、最終的に首都高を地下などに移設・再構築することにより日本橋川の再生を図るなどの提言がなされて以降、具体的な動きはありません。
都議会民主党は、この間、中央環状新宿線の全線開通など、都内の道路交通の状況も大きく変化してきていることも踏まえ、三環状道路完成後の都心環状線撤去案を、都として検討することを提案。それに対し、都は「長期的課題」と答弁しています。
絶対数の不足するバイク駐車場整備を

近年、大型スクーター等の普及等により、繁華街や駅前の歩道空間を中心に多数のバイクが放置されるなど違法駐車が大きな問題となっています。
バイクの駐車場数、収容台数は増加傾向にはありますが、依然として絶対数が不足していることは明らかであり、未だ問題解決には至っていません。
都議会民主党は、都が様々な施策を講じてバイク駐車場の整備を促進するとともに、区市に対してバイク駐車場の附置義務化を働きかけることを求めました。
八ッ場ダム再検証へ 新たな水需要予測せよ
国では今年の秋を目標に、八ッ場ダムの必要性についての再検証を進めることとしています。これに対して都は、極力早い時期に結論を出すよう求めています。
現在、国は都が平成15年に予測した古いデータを用いて利水面での検証作業を行なっており、これでは、誤った結論が導き出される恐れがあります。
一方では再検証を早くしろと言いながら、そのための検証材料は古いままです。このようなことでは、都の主張と行動は、全く矛盾していると言わざるを得ません。
都議会民主党は、23年度中に策定する基本構想の中で将来の水需要を示すのではなく、今すぐにでも、八ッ場ダムの必要性の再検証のため、まず先に、都が国に対して新たな水需要を示すことを求めました。
伊豆・小笠原諸島の航路確保を

伊豆・小笠原諸島航路は、島民にとつては本土との交通・物流手段として欠くことのできない生命線となっています。
しかし、現在、東京の島しょ地域に就航している船舶の多くが既に耐用年数も過ぎ、使用限界の目安となる時期に近づきつつあります。また、新船の建造には、設計から竣工までおよそ2年を要することから、都議会民主党では早急な対応が必要だとして、今後の伊豆・小笠原諸島の航路確保について都はどのように関与していくのか質問しました。

![[前都議会議員] たきざわ けいいち](/img/common/header/h_header_id_1.png)